

BLOG
2025.07.19
豆知識
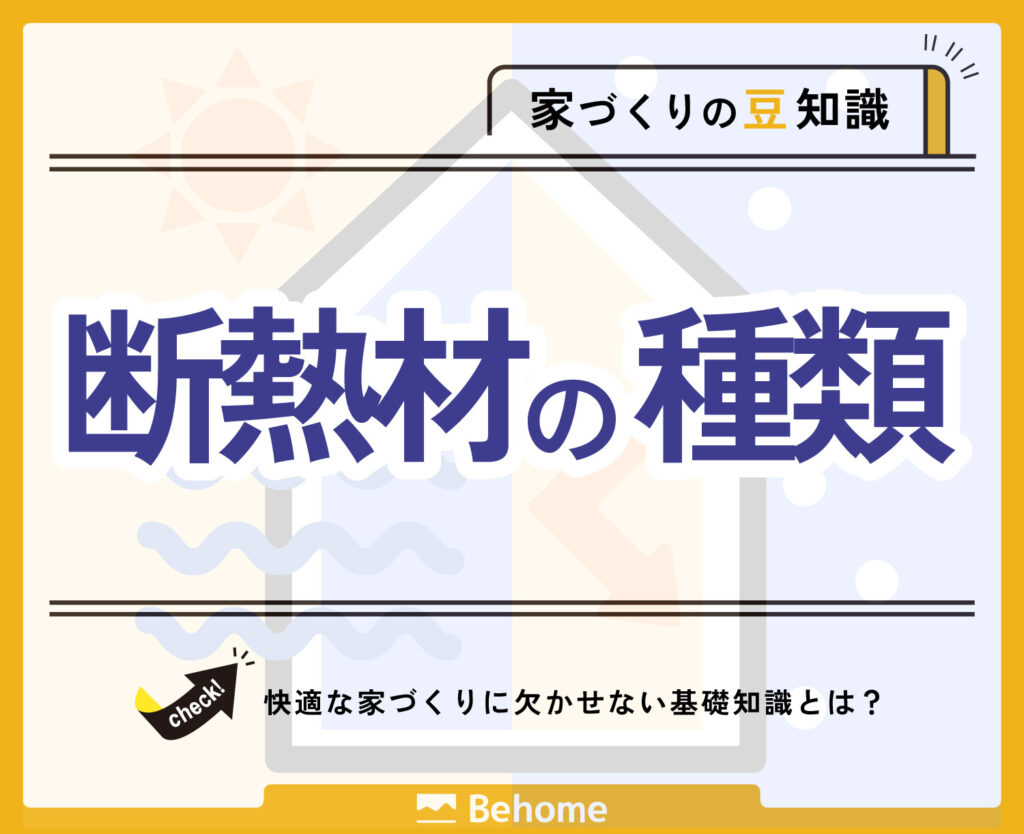
を高める断熱材は、家の快適性を大きく左右する要素です。
夏の暑さや冬の寒さを和らげ、室内の温度を安定させます。
過ごしやすさだけではなく、省エネにもつながります。
光熱費や環境負担を減らすためにも、重要な建材です。
しかし、断熱材は種類が多く、家づくりの際に選び方に迷う方も少なくありません。
この記事では、断熱材の基本から選び方まで解説します。
住まいに合った断熱材を見つけるヒントとして、ぜひ最後までご覧ください。
断熱材は、家の快適さを支える重要な建材です。
目に見えない部分に使われますが、その働きは大きいです。
断熱材は、外気の影響を室内に伝えにくくします。
夏の暑さを遮り、冬の冷たい空気を室内に入れません。
その結果、エアコンや暖房に頼りすぎずに済みます。
一年を通して、温度のムラが少ない快適な空間づくりができます。
断熱性能が高いほど、冷暖房の効率が上がります。
部屋が冷めにくく、暖まりやすいため節電になります。
特に冬場の暖房費を抑えたい方には大切な要素です。
長く住む家だからこそ、経済的な効果も見逃せません。
断熱材には、結露の発生を防ぐ効果もあります。
温度差による結露は、カビや腐食の原因につながりかねません。
天井裏や壁の中でカビが発生すると、健康にも影響します。
見えない場所こそ、しっかり断熱しておきたいところです。
断熱が適切でないと、結露や湿気が構造体に悪影響を与えます。
木材が腐ったり、鉄がさびたりする原因にもなります。
つまり断熱材は、住まいの耐久性を支える存在なのです。

断熱材には、大きく3つの種類があります。
それぞれに特徴があり、適した用途も異なります。
まずは、基本の種類から順に見ていきましょう。
繊維系は、ガラスや鉱物を細かくした素材です。
住宅で最も多く使われている断熱材の一つです。
代表的な繊維系断熱材が「グラスウール」です。
リサイクルガラスが原料で、軽量なのが特徴です。
安価で入手しやすく、扱いやすい点が魅力と言えます。
壁や天井に使われ、防音性にも優れています。
一方で湿気に弱く、施工の精度が問われます。
同じ繊維系では「ロックウール」もあります。
火山岩を原料とし、不燃性に優れている素材です。
音を遮る力も強く、集合住宅に向いています。
ただし水を吸いやすいため、防湿処理が必要です。
プラスチックを発泡させて作る断熱材です。
熱を伝えにくく、水にも強いのが特徴です。
「ポリスチレンフォーム」は、床や基礎に使われます。
熱を通しにくく、軽くて加工もしやすい素材です。
断熱性とコストのバランスが取れた選択です。
「ウレタンフォーム」は現場で発泡するタイプです。
細かいすき間にも密着し、高気密を実現します。
優れた性能を持ちますが、費用はやや高めです。
どちらも耐水性があり、外張りにも適しています。
ただし、火に弱い点があるため補強が必要です。
環境に配慮した断熱材を選びたい方におすすめです。
自然素材由来で、室内の空気をきれいに保ちます。
「セルロースファイバー」は古紙を再利用した素材です。
調湿性や防音性に優れ、結露を防ぐ働きもあります。
燃えにくいように処理されており、安全性もあります。
ただし、施工には専門の技術が必要です。
「木質系断熱材」も人気が高まっています。
木材を細かく加工し、断熱材として再利用します。
サステナブルな暮らしを求める方に選ばれています。
自然素材は、快適さと安心感の両方を叶えてくれます。

断熱材は、ただ性能が良ければいいわけではありません。
使う「場所」によって、適した種類が異なります。
それぞれの部位に合わせて、最適な素材を選びましょう。
屋根は、太陽の熱を直接受ける部分です。
断熱材がないと、夏は室内が非常に暑くなります。
グラスウールやロックウールがよく使われます。
断熱性能が高く、施工も比較的しやすいからです。
発泡プラスチック系も外張りに使われることがあります。
屋根に断熱材を使う際は「厚み」も重要です。
暑さ対策として、十分な厚さを確保しましょう。
また、天井と屋根の両方に断熱材を入れる方法もあります。
冷暖房効率がより高まり、光熱費の節約になります。
壁は、外気との接触面積が広い部分です。
そのため、断熱性能が暮らしに直結します。
壁の断熱には、グラスウールがよく選ばれます。
施工しやすく、コストも抑えやすいのが特徴です。
発泡系の断熱材を壁の外側に使う方法もあります。
「外張り断熱」と呼ばれ、断熱のムラを減らせます。
建物全体を包むように断熱できるのが利点です。
壁は音の出入りが気になる場所でもあります。
防音性を意識して、素材選びをするのもよいでしょう。
また、壁の厚みによって選べる断熱材も変わります。
そのため、設計段階から相談しておくと安心です。
床下は、冷たい空気が上がりやすい場所です。
断熱材が不十分だと、冬に足元が冷え込みます。
発泡プラスチック系の断熱材が多く使われます。
耐水性が高く、床下の湿気にも強いからです。
「基礎断熱」の場合は、建物の外周に施工します。
断熱性が高く、床下空間も室温に近く保てます。
一方「床断熱」は、床の裏側に断熱材を入れる方法です。
どちらもメリット・デメリットがあるため、地域性や家の構造に合わせて選びましょう。
床下の断熱がしっかりしていると、住まいの快適度が大きく変わります。
冷気をシャットアウトできるため、暖房効率も上がります。
断熱材の良し悪しは、見た目では分かりません。
そこで役立つのが、客観的な「性能指標」です。
ここでは、代表的な基準を3つ紹介します。
熱伝導率は、素材そのものの性能を示す数値です。
熱の伝わりやすさを「W/m・K」で表します。
この値が小さいほど、断熱性能が高くなります。
たとえば、グラスウールは0.035前後が一般的です。
発泡プラスチック系はさらに低く、高性能です。
ただし、施工状態によって実際の性能は変わります。
数値だけでなく、施工精度も重視しましょう。
UA値は、住宅全体の断熱性能を示す指標です。
壁・屋根・床など外周部を通じた熱の逃げやすさを表します。
数値が小さいほど、断熱性の高い住宅といえます。
たとえば、北海道では0.36以下が基準とされています。
地域ごとに適正な基準が定められているのが特徴です。
UA値は、建物全体の設計と深く関わります。
性能を高めるには断熱材選びだけでなく、窓や換気計画も大切です。
断熱等性能等級は、国が定めた住宅の性能基準です。
等級は1〜7まであり、数字が高いほど性能が優れます。
現在では、最高等級が「7」に引き上げられました。
ZEH基準の住宅は、等級5〜6に該当します。
等級は、断熱材の種類や厚みの目安にもなります。
家を建てる前に、目指す等級を決めておくと安心です。

断熱材は、ライフスタイルや価値観にも関わります。
住まいに合った断熱材を選ぶこと。
それは、より快適で満足度の高い暮らしにつながるでしょう。
建築費を抑えたい場合は、価格と性能のバランスを重視しましょう。
グラスウールは比較的安価で流通量も豊富です。
断熱性能も一定以上あり、信頼できる素材です。
量産型の住宅や建売住宅でも多く使われています。
ただし、施工不良があると性能が下がります。
そのため、すき間なく丁寧に施工する必要があります。
コスト重視でも、品質管理は見逃せません。
光熱費の削減を重視したい方には、断熱性能の高い素材がおすすめです。
発泡プラスチック系は熱伝導率が低く、屋根や外壁の外張り断熱に向いています。
特に、ウレタンフォームは密着性が高く、すき間なく断熱できるのが大きな利点です。
暖房効率が上がることで、電気代の節約にもなります。
長期的に見て、トータルコストを抑えたい方に最適です。
自然派志向や健康への配慮を大切にしたい方は、エコ素材の断熱材を検討してみましょう。
セルロースファイバーは再生紙を原料とし、調湿性や防音性に優れた断熱材です。
化学物質の使用が少なく、空気環境にもやさしいです。
小さなお子様やペットと暮らす家庭にも安心です。
木質繊維系の断熱材も木のぬくもりを感じられ、心地よい住環境になります。
天然素材は、環境への配慮を家づくりに反映したい方に適した断熱材です。
寒さが厳しい地域では、断熱材の選定が重要です。
外気温に左右されにくい家づくりが求められます。
断熱性能が高く、気密性も確保できる素材を選びましょう。
厚みのある外張り断熱と組み合わせるのも効果的です。
高性能住宅やZEH住宅を目指すなら、
等級6以上の断熱等性能を目安にすると安心です。
設計段階から施工会社とよく相談し、
地域性に合った断熱仕様を計画しましょう。
断熱材は種類や性能だけで選ぶのではなく、施工方法や住まいとの相性も大切です。
ここでは、選定時に見落としがちな注意点を紹介します。
高性能な断熱材でも、施工が雑だとその力を発揮できません。
特に繊維系はすき間ができやすく、熱が逃げる原因になってしまいます。
現場での断熱施工の精度はとても重要です。
信頼できる施工会社を選ぶことが第一歩です。
経験や実績のある業者かどうかを見極めましょう。
事前に断熱の施工方法を確認しておくのも安心です。
断熱性能だけを重視すると、
湿気や結露の問題を見落としがちです。
とくに気密性が高い住宅では、
湿気がたまりやすくなります。
断熱材だけでなく、防湿材や通気層の設計も必要です。
湿度をうまく逃がす仕組みを組み合わせましょう。
結露はカビの原因になり、建材を傷めることもあります。
健康面にも影響するため、軽視できません。
住む地域の気候によって、断熱材の種類や厚みは変わります。
寒冷地では熱を逃さない厚い断熱が求められます。
一方、温暖地では通気性を意識することも大切です。
また、湿度が高い地域では吸水性のある素材は不向きです。
地域の特徴を理解し、それに合った仕様にしましょう。
気候に合わない断熱材を使うと、快適さが損なわれて劣化も早まります。
初期費用の安さだけで断熱材を決めると、後々の後悔につながることもあります。
断熱性能が高いほど冷暖房費が抑えられ、長期的にはコストメリットが得られます。
また、耐久性の高い素材を選ぶことで、将来のメンテナンスコストも軽減できます。
価格・性能・将来性のバランスを考えながら、長く快適に暮らせる断熱材を選びましょう。
断熱材は、家の快適さを支える大切な素材です。
種類ごとの特徴を知り、住まいに合うものを選びましょう。
性能だけでなく施工の丁寧さや湿気対策、地域の気候に合うかどうかも見逃せない視点です。
自然素材にこだわるか、費用を抑えるか…
家づくりの方針によって最適解は変わります。
光熱費や住み心地にも関わる断熱材は、一度きりの選択で長く暮らしを左右します。
安心して暮らせる住まいのために、断熱材選びにも、しっかり目を向けていきましょう。
ビーホームでは、熊本で地域密着のハウスメーカーとして、気候に合った断熱材を提案しています。
自由設計ができる高性能住宅をコスパよく建てるなら、ぜひ当社へお任せください。